|
たらちね追慕 = 母 50回忌を迎えて = |
|
第 一 部
私は最近大阪市立大学医学部付属病院-略して市大病院へ通院しています。 この病院は昨年五月改築オープンしたばかりですが、旧大阪商科大学卒の私には大阪市立大学は母校となり、それが通院のきっかけです。 持病の喘息の治療が目的で昨年の十月以来通院しています。 お陰様で病状がボツボツ軽減してきまして喜んでいます。 序ながら家内も三月頃から通院しています。 今年五十回忌を迎える母タミは改築前のその病院 -当時は大阪市立南市民病院という名称でしたが - に入院中に死去しました。 その時点からはるか半世紀を経ていま私が同じ病院へ通院していることに何か運命的なものさえ感じます。 JRの天王寺駅で降りて病院へ向かう道すがらよく当時のことを思い出します。 父亡き後五人もの男の子ばかりを育てあげてくれた母の苦労を思うと今でも涙ぐむ思いを禁じ得ません。 もう一つ天王寺についての忘れ得ない思い出があります。 何才頃だったか、その当時の大人は誰も生存していませんので確かめる術もないのですが、小学生になる一年位前の年頃だったのでしょうか。 当時父の俊雄は天王寺小学校の教員をしておりましたが、ある日父は私一人を連れて学校へ出かけたことがあったのです。 兄もいたのになぜ私一人だけだったのか知る由もありませんが、その時学校はガランとしていて生徒達などは誰もいなかった記憶があります。 学校へ着いてから父は私にここで待っているようにいいつけた後広い階段を上がって二階の方へ消えました。 私にはその階段が禁断の通路のようでとても上がっていけないような気持ちでいたことを覚えています。 かなり待たされて少し不安になった頃に父が二階の奥の方から私の名前を二三回呼びました。 すぐ上がっていけば何事もなかったのに私にはとてもできなかったのでした。 私はたちまち気も動転して泣きながら校門と階段下との間を走り続けました。 その間年配の守衛さんが怪誇な顔をして私を見つめていた記憶が今でも眼前に浮かびます。 なぜあの時私に一声かけてくれなかったか、私は子供心ながら心中でそれを期待していたことさえ覚えています。 いつの間にか私は泣きやんで、学校から街頭へ出ていったらしいのです。 その頃阿倍野斎場が近くにあって、キンキラキンの霊枢車が時々走っていました。 乗用車自体が今よりずっと少なかった時代でしたから、今まで見たこともない珍しい車がとても豪華に見えたのです。 このことを私は母に何回か話した模様です。 そのうち迷子として警察に保護されたはずですが、そのいきさつはよく覚えておりません。 ただ交番にいる私を大勢の人々が覗き込んでいるのを何だろうかと戸惑っていた記憶が甦ります。 父が叔父達と一緒に引き取りに来てくれたことや伯母から絵本をもらったこと等はかなり良く覚えています。 その絵本に描かれていた万華鏡のようなカラフルな武将の面影の印象が強く残っています。 その後それほど豪華と思った絵本に出会ったことはありません。 母タミは当時の南河内郡藤井寺大字津堂二六番地の地で父藤井増吉母サキの次女として明治二六年八月一日に出生しましたが、当時の中河内郡中高安村大字万願寺第十一番屋敷の円光寺住職秦俊雄と婚姻し、大正七年四月二四日入籍したと記録されています。 父俊雄は祖父徳誠と祖母フジノとの次男(ただし異母兄の長男南岳がいたので戸籍上は三男)として明治十五年二月二六日に出生しています。 その時は父三六才、母二六才で当時としてはかなり晩婚だったようです。 すでに記しましたように、母は五人の男子ばかりを設けました。 敏(さとし)、鼎(かなえ)、享(すすむ)、昭、修の五名です。 一人くらい女子が生まれていたらという返らぬ思いに駆られますが、母の生存中はそんなことすら考えもしませんでした。 父は戦前の典型的な雷親父でしたが、母は対照的に従順な妻としてかしずく如く内助の功に徹していたことを痛々しく思い出します。 父は学校へ出かけるとき門をでた所から火の用心に気をつけてと大声で母へ叫ぶのが常でした。 門の方から呼びかけるのが習慣化していて近所の人達にも良く聞こえていたようです。 母は村の娘たちに裁縫を教えていました。 彼女たちはお針子と呼ばれていましたが、これは祖母の代から引き続いていたと聞いておりました。 娘たちが回し読みしていたのでしょうが、「キネマ旬報」のようなタイトルのついた雑誌が転がっていて良く分からぬままぺ-ジを繰っていたことを覚えています。 お針子さんがまだ勉強している時間帯に父が帰って来たとき慌てて席を立つ母の姿が目に浮かびます。 父は肥満体で無類の酒好き、思えば典型的な高血圧症タイプでした。勤務していた天王寺小学校で教員の身体検査を受けたときすでに二百を越す血圧値があったのです。それでも父は健康体だという自信(実は過信)で余り気に留めていないようでした。 ただ脚気の持病ということで、その対応をしていましたが、いまから思いますと高血圧による腎臓病が進行していたと疑わざるを得ません。 父が病床についたのは昭和六年の十二月の末で急に舌が回らなくなったということがきっかけで当時の八尾町沢の川通りの池田医院の池田先生(後で道源医院と改名された)が回診に来られていました。 人力車に乗って来られた先生の診察の終わった後、車夫へ渡す心付けを急いで包んでいた母の姿が記憶に良く残っています。 その前年に長兄の敏がどうにか旧制八尾中学校に合格して一安心していた父でしたが、それでも兄を病床へ呼びつけ、そこで座ったまま机の前で対座していた彼の勉強に付き合っていたのです。 あまり勉強に身を入れなかった兄には辛い一時であったようです。 二回ほど軽い発作の後三回目の発作が致命的でした。昭和七年二月二十日の朝はやく二か月の療養期間を経て逝去しました。 私はその時四年生の第三学期に入っていましたが、担当の先生からすぐ帰宅するように言われました。 母には晴天の震露だったようです。帰宅すると亡くなった兄と丁度同じような大きないびきをかいていました。 その後の慌ただしい葬儀の模様など断片的ながら覚えていますが、キリがありませんので省略します。 天王寺小学校の教え子達が大勢参列していたのを良く覚えています。出棺する父に向かって「この子達を残してお父さん1…」と取りすがって号泣した母の姿はつい昨日のような光景として甦ってきます。 父は満五十歳直前、母三十九歳でまだ五人目(末弟修)をお腹に抱えていました。 さぞかし心もと無かったことだろうと今でも思い出します。 父の突然の死で母は随分途方にくれたと思いますが、自分の兄弟や父方の兄弟などの下支えを頼りに父に下付された一時金とお寺の限られた収入とを生活の基盤にしながら、けなげにも我々子供達をなんとしても立派に育てあげる決意をしたようです。 そして父の忘れ形見として末弟の修を生み育てあげることを至上命題としていたようでした。 私も当然ながらお寺の手伝いに駆り出されました。 伯父に当る福万寺の万福寺住職の秦南岳さんの許へ三部経を習うため根気良く自転車で通いました。 今ではあげられることはほとんどなくなっているようですが、難しい漢字ばかりの大部のお経の修得に励みまして、と言うより励まされた訳です。 長兄敏は勉強の方は不得手でしたが、長距離ランナーとして運動は得意でした。私は逆に運動はサッパリでしたが、勉強はコツコツ真面目にこなしておりまして、旧制八尾中学校へ入学してからも成績はトップに近い位置にいました。 自分で言うのも気が引けますが、文部大臣まで務めた塩川正十郎君や剣豪作家の故五味康祐君らの同級生よりかなり上位におりました。 旧制大阪商大予科へも四年終了時点(当時は五年制)で合格できました。 何はなくても学校だけはと言う母の強い期待に副うものでしたし、母もこの点喜んでくれていたと思っています。 その間、時代は年々戦時色を強め中学校では軍事訓練が必須科目でした。 これは商大予科でも同様でむしろ強化されました。 それでも予科の英語の時間には週二回教壇に立った二人のアメリカ人から授業を受けておりました。 しかし時代の流れは戦争拡大の一途をたどるばかりだったのです。 そんな中で私は予科二年の夏の終わり頃肺炎浸潤を患いました。 私自身は夏風邪程度の感覚でおったのですが母は喧しく病院行きを勧めました。 私もとうとう根負けして大阪大学付属病院へ出向きました。福島先生という立派なドクターの診察を受け、病名を告げられて静養のため休学を勧められました。 当時の予科は二学期制を採用していて第一期末の試験が目前に迫っておりましたが、試験勉強に専心するどころではありません。 試験終了の頃まで一か月ほど休学していたように思います。その間に微熱が取れ体調もほぼ回復していたように記憶しています。 今から思うと一番危なかった時期だった訳ですが、母の気遣いや看護の賜物であったことを今更のように実感せざるを得ません。 その頃のことだったと考えますが、母と二人で診察を受けたとき、先生が「お母さんの方が要注意ですよ」とコメントされたことを覚えています。 自分自身が病気を抱えながら子供たちに全身全霊を捧げてくれたことを顧みるとき、不欄な思いに駆られてたまらなくなります。 序ながら私は第二学期の試験には頑張りまして皆乙(評価が80%とされますので全甲かそれに近い成績でないと取れません)をもらい留年せずに済みました。 話が前後しますが、末弟の修が幼少時に肺炎と丹毒と言う大病に罹ったことがありましたが、母はその看病に必死でした。肺炎の時は高熱の続く一週間ほとんど寝ずにかかりきりでした。有難い母でした。 長兄敏は八尾中学からやがて大谷大学へ進学し、ついで現役入隊してノモンハン、中支とあちこち転戦しておりました。 三男享は母の実家の藤井家に引き取られ城東工業学校へ、四男昭も錦城商業学校へそれぞれ進学していました。 昭和二八年一二月八日の大東亜戦争の勃発とともに日本全国は総力戦の渦中に巻き込まれました。 長兄はパターン攻略戦に参加後に除隊となり久し振りにわが家に平穏の一時期が到来したのでした。 大東亜戦争の緒戦の優勢も束の間で戦局は日毎に悪化してきました。 私は昭和十八年九月に無事商大学部を卒業して就職しましたが、翌年の三月に召集を受け、福井県の鯖江連隊へ入隊しました。 ここの訓練は凄まじく、私は体調を崩してまして、一年五か月の召集期間中に二回も入院してしまいました。 今になって振り返りまして、よく死なずに済んだという実感がします。私は兵役延期の特典を得て大学を卒業しましたが、徴兵検査は第三乙種だったので現役入隊はありませんでした。 卒業後やく六か月目に教育召集で入隊したわけです。 地方出身の現役兵の体力のある者たちと一緒でしたから、なかなか太刀打ちできません。 鯖江連隊は迫撃砲を主体とした特殊な連隊で兵員は全国から召集されていました。 撃砲は砲身、砲架、砲座などから構成され、即時分解が可能なため、分解したまま、各分隊でそれぞれを肩にかついで運搬しました。 その中で重量は砲架が約六十キロ、砲座が約五十五キロありまして、野外演習の時には号令がかかるごとに交替で肩に担いで運搬するのですが、砲座の場合、矩形の板状の周囲が尖っていて肩に食い込み泣かされました。 汗を流しながら号令がかかって交替するまで、歯をくいしばってがんばったことを良く覚えています。 兵舎まで数百メーター位に近づくと、分隊長が号令をかけて各分隊ごとに分解した迫撃砲を担いだまま競走させたこともありました。 私は担ぐどころか走ってっいていくのが精一杯という状態で後で受けるであろう「しごき」のことを考える余裕すらありませんでした。 もう一つ忘れ得ない思い出はサイパン島への出撃部隊の見送りでした。 多分第一回目入院下番の後だったように思います。 まだ明けきらぬ早朝、担いだ銃身全部を白布に巻いて、部隊長の訓示の後、隊伍を組んで歩調を揃え、次から次へと営門を出ていきました。見送る側には心中なにか悲壮な思いがありましたが、それをはっきり口に出すことは勿論揮られました。 昭和二十年三月の頃でした。母は思いがけず入院中の私を見舞ってくれました。 入院を繰り返す私は当然のように甲種幹部候補生の資格を外され、乙種幹部候補生いわゆる乙幹に編入されており、当時は伍長の肩章をつけておりました。 そして、二十名位を収容する病棟の部屋長に任命されておりました。 面会室へ出向きますと母が初対面の兄嫁の富子さんと二人で待っていました。 まさかの思いで非常に嬉しかったのを覚えています。 その時に会った母はまだ元気でしたし、母の方でも入院中ながらほぼ普通の体調に戻っていた私を見て一安心してくれたのではないかと思います。 その後除隊して家に戻っていた兄が再召集で鯖江の同じ連隊に入隊してくるというハプニングもありました。 もう夏の頃だったと思いますが、退院して中隊へ帰隊していた時のことですが、給食の量が足りないからなんとかならないかとコッソリ伝えて来ました。 丁度私が中隊長の当番下士官を努めていた時なので、給食担当の兵に頼んで一人分の食膳を用意してもらい、暗くなった頃に窓の外で待っていた兄へ渡したこともありました。 やがて八月十五日の終戦の当日が来ました。 寝耳に水の玉音放送を聴きました。 色々な人が色々な思い出を綴っておりますが、この日を境に日本は大転換をとげました。 遠い古のことはさておき、明治維新と対比できる日本歴史の大変革の時期でした。 八月の終わり頃だったと思いますが、私のような退院下番者などは優先的に除隊を認めると言うことになり帰郷が始まりました。 私はとにかく早く帰りたい一心でせっかく支給を受けたこめ(当時はすでに貴重品でした)も重いためというだけでおっぽりだして営門を出ました。 大阪までは当時の国鉄に乗って帰って来たのですが、城東線(今のJR環状)が不通でした。 大阪駅前で夜明かししたような記憶があります。 それから天王寺を経由して鶴橋に出て帰宅しました。 山本駅で下車して歩き始めると思わず小走りになり、足が宙に浮いてまるで雲の上を歩いているような気がしたことを良く覚えています。 帰宅してびっくりしたのは母がげっそり痩せ下腹が異常に膨れて別人のような姿態をしていました。それでも母は私の除隊を喜んでくれました。 その後、家では看病はとても無理ということになり、大阪市立南市民病院に入院しました。 どうしてこの病院に決めたのかは今思い出せません。 母をリヤカーに乗せて駅まで運びました。出発まえ母はわざわざ門の方まで戻って本堂に向かって手を合わせ頭を下げたまま涙ぐみました。 もう二度と帰ることは無いと思ったのでしょう。 上六からは電車に乗りました。 タクシーなど無い時代で私は抱えるようにして母を病院へ運びました。 兄がいつ除隊してきたか記憶が定かではありませんが、母の死の直前だったような気がします。兄嫁の富子さんも世を去りまして今では確かめようもありません。 母は一か月余り入院していたと思います。 戦争が終わったと言う実感に慣れてくる反面、まだ闇市が本格化していなかった世相と言うこともあって、今では想像もできない日常でした。 病院の近くの路上でたまたま売っていた林檎一個を買い求めてきたことがあります。 すり下ろした林檎をそのまま母の口へ流し込んだのですが、母は珍しくおいしそうに食べ、もっと欲しがりました。 もう一度買い求めに出向くとその場所には誰もおりませんでした。それは当時まさに貴重品でした。 その果物も弱り切った母には受け付け無かったみたいでした。 私は母が回復不可能だとは覚悟していましたが、最後の時が迫っているという実感が不思議に無くて、なにかその状態がまだまだ続くように錯覚していたような精神状態でした。 林檎を食べてから二、三日たった頃かと思いますが、ベッドの下で用を足したいと言いましたので、弱り切った母を支えてフロアーへ下ろしました。 暫く外で待っていてまたベッドへ戻しました。下痢の状態だったと思います。 その時なにか非常に苦しそうな表情を浮かべていたことを覚えています。 母は私に申し訳ないと謝っていました。 そして、その日が母との永別の日だったのです。 同じころ、ふと目覚めた母が「津堂にいると思ったのに…」と独言を言っていました。 死が迫って夢の中で心が故郷に帰っていたのだと後で思いました。 その頃は富子さんと昼夜交替で付き添い、私は昼の番でした。母の容体が悪化していたのは分かっていましたが、夕刻暗くなってから母に声をかけて帰りました。 二人も居るわけにもいかずと思い、後髪を引かれる気持ちの切なるものがありました。 翌日お昼頃に母が死去したと知りました。 (兄から聴いたような気がします。 これが唯一の兄の除隊時期についての記憶です。) その時私はたまたま裏の畑で鍬を使っていましたが、母の死を知って身体全体が地の奥底へ吸い込まれるような感じがしました。 この感じは今でもハッキリ意識に残っています。 病院から母の遺体の引き取りが大変でした。 丁度近鉄へ復職していた弟の享の配慮があって電車で藤井寺へ運び、ひとまず実家の藤井寺に安置しました。 母への良い供養になったと思います。 母の遺体はそれから万願寺への長い道程を自転車で運びました。 駒太郎伯父や九一叔父らと一緒に私もその運搬に同行しました。 駒太郎伯父がしっかり自転車のハンドルを握り後の者たちが丸い棺桶を両側から支えながら入念に道中した模様が眼前に浮かびます。 時々交替しましたし、私も少しハンドルを持ったように思いますが、はっきりした記憶はありません。 それから慌ただしい葬儀の段取りがありました。 その中で一番記憶に残っている情景があります。九一の叔父が母が日頃着用していた黒の衣を母に着せながら「姉さん!これを着てお逮夜参りをようしてくれましたなあ。 いいとこへいっとくなあれや…」と涙声で呼びかけてくれました。 私は感情が昂まって声も出ませんでした。 行年五十三歳、死去の日は昭和二十年十月二十九日でした。 母が亡くなって心の中にぽっかりと大きな穴が開いた気持ちが長く続きました。 もう一つ母の法名について記して置きたいと思います。 法名は他の宗派では戒名とか法号とか申しますが、浄土真宗では戒律を授けると言うことがありませんので、すべて法名で統一されています。 またお寺の住職や坊守(住職の妻)は本山に申請すれば無条件に院号法名を下付されます。 さらに円光寺では代々何々院という三字の院号の中で「乗」と言う文字を使用する建前となっていました。 私はいろいろ考えまして、院号については「慈乗院」と言う呼称が母にふさわしいと思いました。またそれに続く法名については母も欣求したであろう極楽浄土から「浄」の一字を、父の法名「悉乗院釈俊晃」から「晃」の一字をそれぞれ取り入れて「釈尼浄晃」として提案し、母の院号法名はそのまま採用されました。 最近になって私は「浄」の字は古来男性に使用するのが習わしだということを知りました。 歴史上の法体の人物を思い浮かべて納得しました。 今後円光寺において、私が申し述べましたルールが堅持されることを希っております。 母の思い出は書き尽くせるものでないことを痛感します。 また書くことを控えたところもあります。 母のいない人ほど母への思いが強くなると言うことですが、早く母を亡くした私にはその思いが一段と強いのだと思います。 母の五十回忌を迎えるに当たり、私は当時の模様を是非記録しておきたいとの決意に駆られた次第です。 長寿日本の象徴的存在の例のきんさん、ぎんさんと同年代の母がもし生きていれば百歳を超えることになります。そして、彼女らと母との余りにも大きな落差に複雑な思いに駆られます。 五十回忌で母の思い出が尽きるものではありません。 六十年、七十年…と我々兄弟が生きている限り、自己犠牲に徹した立派な母に育てられたことを反芻し乍ら、また誇りに思いながら、生きて行きたいものと念じています。 今の世情を思うとき、この思いは一層切なるものがあります。 同時に、我々の若い肉親たちに我々の思いの一端でも分かってもらいたいと言う密かな願いがあるわけです。 平成六(一九九四)年九月九日 以上
|
|
第 二 部
今や日本人はGNPでは世界のトップに位するほど豊かになりました。 戦中戦後の最貧窮時代を経験した私などには夢のような豊かさです。 しかし精神面ではいかがでしょうか? 宗教に無関心派が着実に増えて、他方に様々な新興宗教が栄えています。また仏教そのものへの理解もお粗末の限りです。 さらにプロの方々の説法は俗耳に入りにくい感じはいなめません。 最近私が読んだ作家の司馬遼太郎氏の一文に引かれました。 仏教の全体像を簡潔かっ分かり易く捉えておられるのは同氏が専門の宗教家でないため、宗派的な繁雑さや抹香臭さがなく、かえって新鮮に受け入れられるからでしょうか?以下にその全文をご参考に供します。 聖たち 司馬遼太郎 仏教にあっては、一切は空である。 あわせて、万物は轟々と輪廻する。 従って、初期仏教には天国も極楽もなかった。悟りをひらく以外に、光明はなかったのである。 釈迦の没後、数百年経って、様子がかわった。 インド文明圏の一角で成立したらしい『阿弥陀経』が、キリスト教が天国を説くようにして、極楽の存在を説きはじめたのである。 本来の釈迦の仏教とは別系列の観があるといっていい。 是従リ西方、十万億仏土ヲ過グレバ、世界有リ。 名ケテ極楽ト曰フ。 と『阿弥陀経」にいう。 極楽は浄土ともよばれる。 浄土はいくつもある。強靭が主宰する浄土もあれば、また薬師があるじの浄瑠璃浄土もあるが、結局、阿弥陀如来が主宰する極楽浄土が、大きく流布した。 なにしろ阿弥陀如来は、如来自身の固有の願い(本願)によって、「ひとびとが私(阿弥陀如来)の名をたとえ十遍でもとなえるなら、西方十万億仏土に往かせ、そこで、生れさせよう(往生)」というものなのである。 このため圧倒的な魅力をもった。 インドにおける阿弥陀如来の成立にはイラン思想が入っているといわれている。 ひょっとすると、初期のキリスト教の破片も入っていたかもしれない。 ただキリスト教と決定的にちがうのは、ゴッドが厳格な父性であるのに対し、阿弥陀は人間の弱さに対して寛容な母性であることである。 キリスト教の場合・天国へゆくのに生前の論理的所業が審査される。 『阿弥陀経』にあっては、弥陀の御名をとなえる(南無阿弥陀仏を唱名すること。念仏)だけで、罪ある者も、浄土へゆける。 ついでながら念仏は呪文ではなく、単に感謝のあいさつである。 阿弥陀信仰は、中国に遷った。 四世紀半ばごろの中国に慧遠(三三四〜四一六)という僧がいた。 かれは長江流域の廬山のふもとに東林寺をたて、齪轡枇どいう念仏結社をおこした。 これが中国浄土教のはじまりといわれている。 廬山の白蓮社は、その後の日本の浄土教とはちがい、禅道場のように胤騨をたて、戒律もうるさかった。藍山ししたにの風にちかい日本の寺は、京都鹿ケ谷の法然院だけだといわれている。 浄土教は日本につたわって厳格さがやさしさにかわった。 やさしさというのは、易であってもよく、優であってもいい。 日本における浄土教の祖は、十一世紀、平安中期に酬雌で学んだ源信(九四二-一〇一七)だった。顧航僑静ともよばれ・叡山の山中の櫛鵬に隠棲したことで、 「横川の僧都」 とよばれた。紫式部とほぼ同時代人である。 『源氏物語』のなかで、「その頃、よかは(注・横川)になにがし僧都とかいひて、いと尊き人住みけり」というのは源信のことである。 浄土信仰の高僧にかぎって"尊し“と形容する場合が多い。 おそらく"捨てる“という精神と一体だったからにちがいない。 かれは日本ではじめて詳細に地獄の情景をのべた。 そのことで平安貴族を鞍毘させ、廃市浄土の風がかれらのあ いだでひろまり、浄土教美術が流行した。 源信と同時代のちかい関白藤原頼通が、宇治の別荘を改築し 、丈六の阿弥陀如来座像を安置し、阿弥陀堂(鳳團堂)と名づ けた。 まわりに林泉をめぐらし、夜になれば金色の阿弥陀如来のお顔を灯明が照らし、堂外からみても、かがやいて見えた。当時、なお極楽思想を疑う人が多かったが、「極楽いぶかしくば、宇治の御堂を礼すべし」といわれた。浄土思想は教学よりも造形美術からはじまったのである。 それでもなお叡山の正規の僧(官僧)にあっては、浄土思想などという易行道にとりつかれる者はまれだった。 法然(一一三三〜一二一二)がはじめて官僧である栄誉を捨て、浄土教という多分に民間的な宗教に入った。官僧が聖(非僧非俗)に身をおとすのは、当時よほどのことだったらしい。 法然は里に降りて説法をし、浄土宗をひらいた。宗というのは思想体系のことである。当時は教団をさすことばはなかった。 法然は生きながらにして極楽の風に吹かれているような人柄 であったらしい。 以下は『徒然草』第三十九段にある咄である。 ある人が、法然上人にむかい、思いつめて相談した。私は居眠りするくせがございます。お念仏の最中に居眠りをしてしまいますが、どうずればいいでしょう。と問うと、「目のさ(覚)めたらんほどに、念仏し給へ」と法然がいった。「いと尊かり」と兼好が結んでいるが、捨て去って凡夫の場にいる法然が、おなじ凡夫である相手をいたわっているからこそ尊いのである。 法然は日本の浄土教を確立した。 かれが大きく描いた輪郭を、弟子の親鶯(一一七三〜一二六二)が哲学化した。日本仏教は親驚によってはじめて教義と教学を持ったことになる。 親鷺がみずからその体系をよんで「浄土真宗」とよんだのは、さきの「浄土宗」と同様、体系だけをさしている。さらに、「親鷺は弟子一紙ももたずさふらふ」と『噺黙秘』のなかで言い、教団をもたないことを明言した。 こんにちの本願寺教団は親鷺から八世の子孫の蓮如(一四一五-一四九九)がたてたもので、親鷺の無教会主義とは異なる。 『嘆異抄』は、十三世紀の作品ながら、明治以前の思想的文章の第一等のものである。関東に住む唯円という非僧非俗の者が、十余カ国の塘をこえて京にのぼり、信仰についての疑いを親鶯にただして書きとった。 「念仏をとなえると騨蹴蹴聾したくなるということですが、私はすこしもうれしくならないのです」と、唯円がきいた。また、 「極楽とはすばらしい所だそうですが、それならすぐにでもゆきたいのに、いっこうにそういう心がおこりません」 ともきいた。ひらたくいえば、死にたい気持ちがおこりません、という。浄土教は、死をもって救われるとし、また死は甘美であるともしている。 「唯円房もそうか、じつをいうと私もそうなのだ」 と、親驚は意外なことを告白する。一宗の創設者でありながら、みごとに虚飾を捨て去っていて、ただいのちを持てあまして生きている仲間という次元しかない。親鶯の用語でいう同朋である。 法然や親鶯とは、べつな山河を歩いた人に、'.圃(=三九-一二八九)がいる。 伊予の大富豪の子に生まれ、幼いころに出家して、はじめは天台を学び、ついで法然の法流を学んだ。ただし法然の徒ではなく、みずから思索して独自の浄土門をひらいた。生涯歩きつづけ、 「遊行上人」 とよばれた。捨聖ともいわれた。 すべて捨て、ついには南無阿弥陀仏と唱えて浄土にゆきたいという自分まで捨て、捨てるべきなにもなくなつみよ-つご・つたとき、虚空に名号(南無阿弥陀仏)だけがあるという境地に達した。禅でいう悟りといえる。 旅に病んで死ぬとき、いっさいの著作をすて、し上うぎょう 「一代聖教みなつきて、南無阿弥陀仏になりはてぬ」といった。凄味がある。 以上、法然、親鷺、一遍をみていると、非仏教のようにみえて、釈迦の仏教にもっとも近かったことがわかる。 親鸞の流れから、妙好人という、禅の悟りそのままの精神像が出現したのも当然なことで、結局は、三人にとっての阿弥陀如来が、空の別名であったのである。 西方十万億仏土というのも地理的呼称ではなく、大乗教典が多用する比楡にすぎない。また空はさびしいものでなく、空こそ光明であるとした。そのために極楽というモチーフを借りたのである。 以上、日本仏教の一特徴について述べた。 (しば りょうたろう=作家・文勢春秋4年3月号「この国のかたち・七十二」) あとがき 私は俳句歴が二十年を超え、日ごろ駄句をひねっておりますが、「母の思い出」の近詠句を下記にてご笑覧に供します。 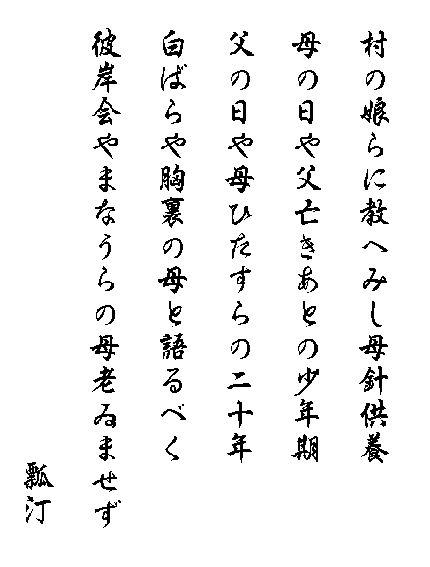 |